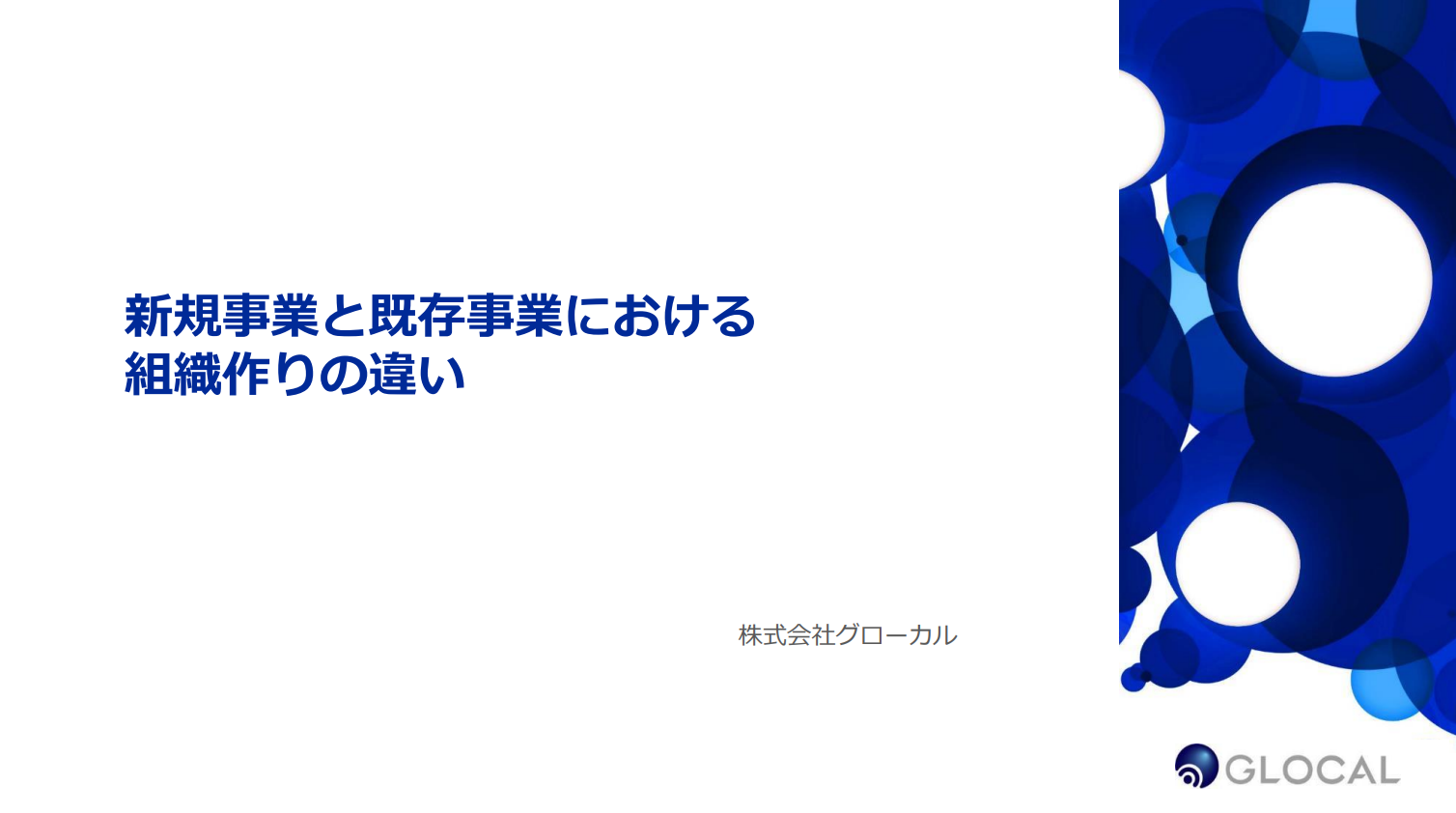失敗しない新規事業の組織体制の作り方 ‐既存事業との違いから考える設計のポイント‐

新規事業を始めたものの、思ったように進まない。メンバーはそろっているはずなのに、仮説検証が進まず、判断も遅れがち──。このような悩みを抱える企業の多くは、「組織体制の作り方」を既存事業と同じ感覚で設計しているケースが少なくありません。
新規事業には、新しい事業を生み出すための前提に合った組織構造や人員配置、評価の考え方が必要です。本コラムでは、「新規事業に適した組織体制とはどうあるべきか?」という問いに対し、よくある失敗パターンと、既存事業との違いを軸にした設計のポイントをわかりやすく解説します。
新規事業の組織作りによくある失敗例
1. 責任の所在が曖昧なままスタートしてしまう
新規事業の立ち上げにおいて最も多い失敗の一つが、「誰が責任者なのかが不明確な状態で走り出す」ことです。立ち上げを命じられたものの、最終的な意思決定権が経営層にあるのか、現場にあるのかがはっきりせず、承認プロセスに時間がかかる。結果として、判断のスピードが遅くなり、変化の激しい環境で競合に後れを取ってしまうという構図です。
2. 兼任体制に頼り、プロジェクトが頓挫する
中堅・中小企業では人的リソースが限られるため、新規事業を既存メンバーの“兼任”で進めるケースが少なくありません。しかし、本業との優先順位の違いから、思うように工数が割けずに頓挫するパターンが頻発します。特に、営業や開発などの中核人材が既存事業で手一杯の状態では、新規事業は常に後回しになりがちです。
3. 評価基準が既存事業と同じで、挑戦が抑制される
新規事業は本来、仮説検証を繰り返しながら方向性を模索するものですが、立ち上げ初期から既存事業と同様の売上・利益目標を課されるケースもよく見られます。その結果、短期的成果ばかりを求められ、リスクを取るチャレンジが避けられるようになります。「失敗できない」という空気感の中で、学習や試行錯誤が進まず、結果として事業が育たないまま終わってしまうのです。
以上のようなよくある組織的失敗は、いずれも個別の問題に見えて、実はすべて「組織体制設計の曖昧さ・準備不足」に根本原因があります。また、新規事業と既存事業において同じ考え方のもと組織構築を行うことで、上記のような問題が発生いたします。
新規事業と既存事業の違いを正しく理解する
1.目的と評価軸の違い
既存事業は、既に成立した市場の中で収益を最大化することが目的です。そのための評価軸も、売上や利益といった短期的な定量成果に集中します。
一方、新規事業は“正しい答え”がどこにあるのかも曖昧な状態から始まるため、仮説検証や顧客の反応、学びの質といった“探索のプロセス”そのものが評価対象になります。
<新規事業>
・目的:仮説検証による事業可能性の探索
・評価軸:学びの質、検証サイクル、顧客フィードバック
<既存事業>
・目的:利益・シェアの最大化
・評価軸:売上、利益、コスト効率、KPI達成度
2.組織文化と意思決定のスピードの違い
既存事業では、リスクを最小化し安定稼働を守るために、慎重で段階的な意思決定が行われます。 一方、新規事業ではスピードと柔軟性が競争力に直結するため、現場が迅速に判断・行動できる組織設計が必要です。
<新規事業>
・特徴:現場主導、フラットな関係性、スピード重視
・意思決定:1〜2階層で即決する体制
<既存事業>
・特徴:階層構造、安定重視、承認プロセスが明確
・意思決定:上層部を通した慎重なプロセス
3.人材に求められる特性の違い
既存事業では、既知の課題に対して正確・効率的に対応できるスキルが求められます。
新規事業では、先が見えない環境で仮説を立て、行動し、失敗から学べる“自走型人材”が欠かせません。
<新規事業>
・必要な特性:不確実性耐性、仮説思考、実験志向、起点を自ら作れる人
・タイプ:動きながら考え、自己判断できる人材
<既存事業>
・必要な特性:正確性、継続力、オペレーション遂行力
・タイプ:ルールを守り、安定的に成果を出せる人材
新規事業と既存事業の違いのまとめ
既存事業と新規事業は、組織内で同時に存在していても、目的・文化・人材要件が根本的に異なります。だからこそ、新規事業を成功に導くには、最初の段階で「既存事業とは異なる設計思想が必要である」という認識を組織全体で共有することが、第一歩となります。
新規事業に必要な役割と人員配置とは?
1.必要なのは「完璧なチーム」ではなく「回るチーム」
新規事業の初期は、事業の方向性や成功確率がまだ定まっていない「探索」の段階です。そのため、部署横断の専任チームや多数の人材を配置する必要はありません。むしろ、「仮説→実行→検証→学び」のサイクルをいかに早く、かつ自律的に回せるかが最重要です。そのためには、以下の3機能を最低限カバーできる体制でスタートするのが現実的かつ効果的です。
2.最小構成で必要な「3つの機能」
多くの企業が誤るのは、新規事業にも既存事業と同様に“完全なチーム構成”を求めてしまうことです。実際には、初期フェーズに必要なのは以下の3機能だけです。
- 戦略設計・意思決定(リーダー/事業責任者)
- 顧客接点の確保と仮説検証(マーケ・営業担当)
- 検証のための最小限の実装能力(開発・実務実行者)
上記の構成は1人が複数機能を担っても構いません。重要なのは“仮説検証のループが回る体制”であることです。
3.社内で足りない役割は“外部”を活用する
中小企業やリソースに限りのある企業では、開発・デザイン・マーケティングなど、内製できない領域が多々あります。そうした役割は外部パートナーや副業人材を活用することを前提に考えたほうが合理的です。重要なのは、すべてを自前で抱えようとするのではなく、事業仮説の検証に必要な最低限の能力を、迅速に使える体制を整えることです。
新規事業のフェーズに沿った組織体制の考え方
新規事業はフェーズごとに課題も必要なスキルも変化します。そのため、初期と同じ体制で拡大を目指してしまうと、どこかで“伸び悩み”が発生します。だからこそ事業のステージに応じて組織を「設計し直す」視点が重要です。
0→1期:「スピードと自律性」
このフェーズは、ユーザーの課題がどこにあり、どのような価値を提供できるかを見極める段階です。事業の「筋が良いか」を判断するために、できるだけ早く仮説を立て、検証するサイクルを回す必要があります。そのため、組織は小規模かつ柔軟であることが重要です。役割分担を細かく決めすぎず、メンバー同士がカバーし合いながら進める方が機動力を保てます。
<組織体制の特徴:少人数・フラット・現場主導>
・チーム構成は3〜5人程度が目安
・経営層と距離が近く、意思決定が速い体制
・役割分担よりも、柔軟に動ける体制が重要
・スピードと仮説検証の回転数を重視
1→10フェーズ:事業化・仕組み化の段階
目的:PMF後の仕組み化
このフェーズでは、一定の顧客から価値が認められ、収益化の兆しが見えてきます。プロダクトを安定して届け、再現性のある運営を行うための「仕組みづくり」が求められます。
<組織体制の特徴:機能別チームを組成(営業/CS/開発など)>
・専門機能ごとに役割を明確化
・属人的な対応からチーム対応へ移行
・顧客対応や運用の標準化を進める
・機能間の連携を支える仕組み(定例会議、情報共有ルールなど)が必要
10→100フェーズ(拡大)
目的:組織化とスケーラビリティ
市場での一定のポジションを獲得し、さらに事業を拡大していく段階です。規模に耐えうる組織基盤を整え、人材を増やしても質を保てる体制が求められます。
<組織体制の特徴:マネジメント強化/評価制度の再設計>
・マネージャーや中間層を配置し、ライン型組織へ移行
・採用・育成・評価の仕組みを制度化
・組織文化や行動指針を明確にし、一貫性のある組織運営を目指す
・指示待ちでなく「自律的に動けるチーム」をつくる
おわりに
新規事業の立ち上げにおいては、既存事業と同じ考え方や体制をそのまま適用してしまうことで、組織が機能せずに停滞するケースが多く見られます。目的、評価の仕方、求められる人材、意思決定のスピード感など、あらゆる面で前提が異なるため、それに合わせた組織設計が必要です。うまくいかない原因の多くは、現場の努力不足ではなく、制度や設計そのものにあります。
だからこそ、事業責任者や経営層が新規事業の前提を正しく理解し、それに合った体制を意図的につくることが重要です。はじめから完璧な体制を用意する必要はありませんが、「何を最優先すべきか」「どこに柔軟性を持たせるべきか」を見極める視点が求められます。本コラムが、自社の新規事業を支える組織づくりの一助となれば幸いです。