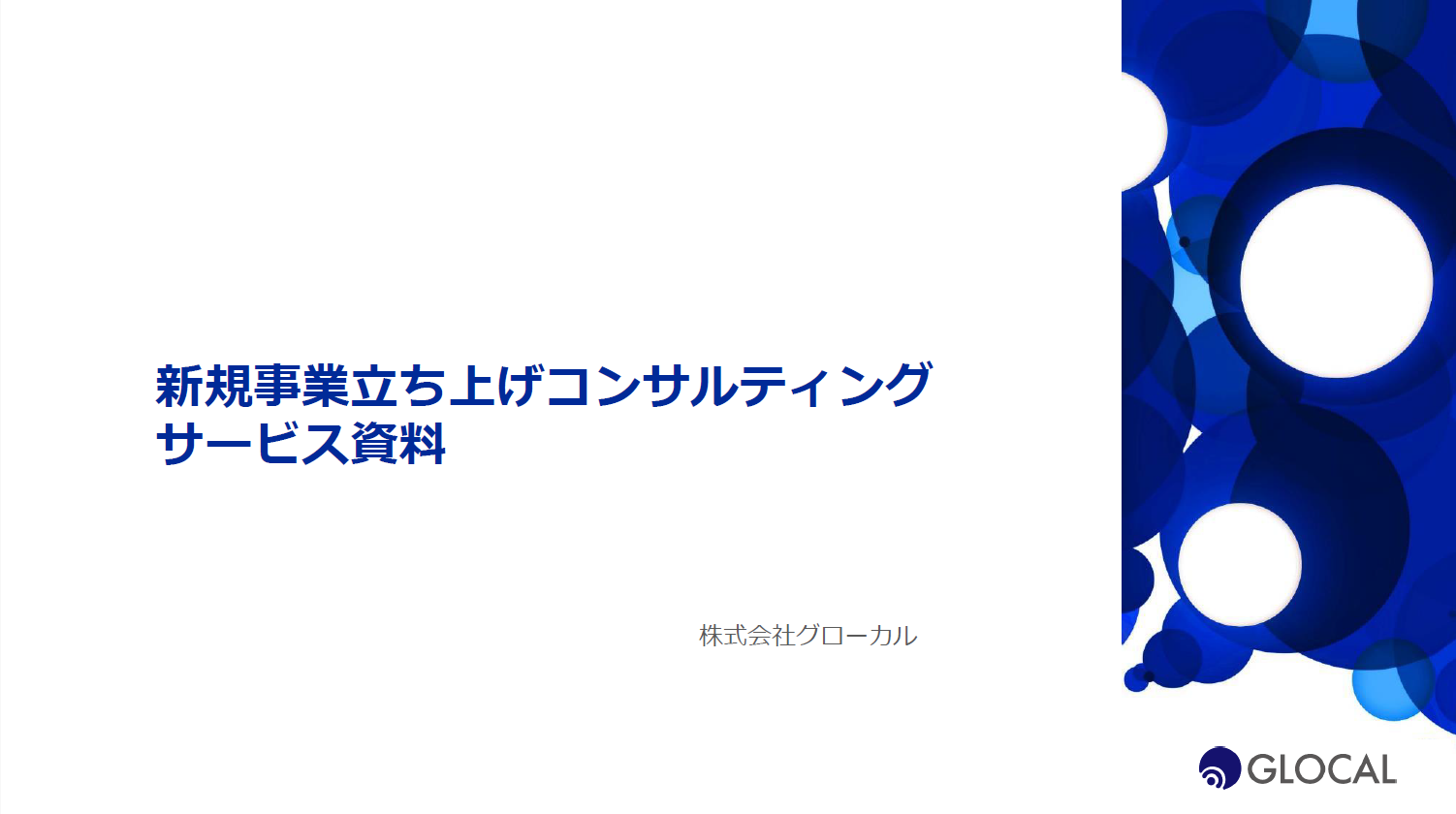新規事業の成功率を上げる方法|企画段階で押さえる5つのステップと実践ポイント

「何度も市場調査や仮説検証を重ねてきた。けれど、本当にこのテーマで進めていいのか──自信が持てない。」そんな不安を抱えたまま、プロジェクトが進まずに止まっている。新規事業に取り組む企業で、こうした状態が続いているケースは決して珍しくありません。特に中堅・中小企業では、限られた人員とリソースの中で取り組むからこそ、「このテーマで本当に成功できるのか」「失敗したらどうなるのか」という不安は大きくなりがちです。その結果、十分な判断材料がないまま、検討ばかりが長引き、プロジェクトが動かなくなってしまうのです。
しかし、ただ悩み続けているだけでは、状況は何も変わりません。成功率を上げるために必要なのは、慎重に考え続けることではなく、“抑えるべきポイント”を明確にし、判断と行動を進めるための土台を整えることです。逆に言えば、その土台がなければ、前に進むべきかどうかの判断さえできません。PoCやローンチを迎える前に、「そもそもこの企画は進めるべきなのか?」という問いに、しっかり答えを出す必要があるのです。
本コラムでは、新規事業の成功率を上げる方法として、新規事業のテーマ企画にてどんなステップで行うべきか、さらにはどんなポイントに気を付けるべきかの解説を行います。
新規事業の成功率は、企画次第で大きく変わる
PoCやローンチ後の成否に目が向きがちですが、実際には、企画段階の設計がその後の成果を大きく左右します。
たとえば──
顧客像が曖昧なまま進めてしまっていた。
技術やアイデアが先行し、誰の課題を解決するのかが見えていなかった。
競合がいない=市場があると勘違いしていた。
社内での期待値や評価軸が揃っていなかった。
こうした企画時における“初期のズレ”を放置したまま検証や開発に進んでしまうと、あとから軌道修正するのは難しく、結果的に失敗のリスクが高まります。
だからこそ成功率を上げるためには、企画段階での構造的な設計が欠かせません。誰に・何を・なぜ提供するのか。そして、その企画が進むべきかどうかをどう判断するのか──。これらを事前に整理しておくことが、成功率を上げるための土台となります。
次章では、そうした企画設計を実践するための7つのステップを紹介します。今の企画を見直したい方も、これから新たに構想を立てたい方も、進め方の指針としてご活用いただけるはずです。
企画時にありがちな失敗のパターン
新規事業が失敗する原因の多くは、検証段階ではなく企画段階に潜んでいます。以下は、事業ローンチ後に「失敗」と判断される典型的なパターンです。
1. 市場規模が不十分
起きる現象:顧客が想定より集まらず、売上が伸びない
原因:「競合がいない=ブルーオーシャン」と誤認
TAM(総市場)・SAM(獲得可能市場)・SOM(実際に取り得る市場)の分解不足
よくある事例:一部の熱狂的ユーザーには刺さるが、国内市場が数億円規模しかない
海外では成立しているが、国内では需要が存在しない
2. 顧客ニーズの理解不足
起きる現象:導入はされるが、利用が定着せず撤退
原因:「製造業向け」「若年層向け」など抽象的なターゲット設定
課題の深掘り不足で「なくても困らない」サービスになる
よくある事例:技術や機能は評価されるが、顧客の実際の購買動機につながらない
PoCで好意的に受け入れられたが、正式導入には至らない
3. 開発・実行が不可能
起きる現象:PoCはできても量産化・運用フェーズに進めず頓挫
原因:必要な技術・人材・資金の精査不足
外部パートナー頼みで内製体制がなく、スケールできない
よくある事例:AIやIoTサービスを企画したが、自社にはデータ活用人材がいない
運用コストが高く、採算が合わない
4. 収益モデルが未検討
起きる現象:ユーザーは増えるが、利益が出ず撤退
原因:CAC(顧客獲得コスト)やLTV(顧客生涯価値)を考慮しない価格設定
「まずは安価にシェア獲得」で赤字構造が定着
よくある事例:月額課金モデルで顧客数は増えるが、広告費を回収できない
利用単価が低く、事業がスケールしても赤字が続く
5. 自社資産(顧客・技術)の活用不足
起きる現象:競争優位性を築けず、既存事業との差別化ができない
原因:自社の顧客基盤・技術資産を事業設計に反映できていない
「ゼロから新規事業を立ち上げる」発想に偏る
よくある事例:既存顧客へのクロスセルを活かせば有利なのに、全く新しい市場に挑戦して失敗、自社の特許技術を使わず、他社と同質化したサービスを展開
これら5つの失敗パターンを防ぐために、次に紹介する「7つのステップ」で企画を体系的に整理していくことが不可欠です。
新規事業の成功率を上げる|企画で抑える5ステップ
新規事業を成功させるためには、企画の各フェーズで「何を確認し、何を防ぐのか」を明確にすることが不可欠です。以下では、各フェーズごとに【活用フレームワーク】【評価観点】【防げる失敗】を整理しています。
STEP 1|目的を定義する:取り組む意義と上位概念を明確にする
活用フレームワーク:ゴールデンサークル(Why/How/What)
事業を「なぜやるのか(Why)」から逆算して定義することで、手段化や迷走を防ぐ
評価観点:経営課題や中長期戦略と整合しているか
事業目的が「売るため」など手段化していないか
防げる失敗:企画の場当たり進行
社内調整不足
STEP 2|自社の立場を把握する:内部資源と制約条件の可視化
活用フレームワーク:SWOT分析(内部資源の強み・弱み)、バリューチェーン分析
自社が持つ顧客・技術・ブランドなどのアセットを棚卸しする
評価観点:他社と比較して明確な優位性があるか
社内のリソースや専門性と乖離していないか
防げる失敗:開発・実行の不可能性
自社資産(顧客・技術)の活用不足
STEP 3|市場と競合構造を捉える:ポジショニングの検証
活用フレームワーク:TAM/SAM/SOM、5フォース分析
市場規模と競争要因を定量・定性で確認する
評価観点:TAM/SAM/SOMを踏まえた現実的な市場規模が算出できているか
“競合不在”が需要不在を意味していないか
防げる失敗:市場規模が不十分
STEP 4|顧客ニーズを検証する:一次情報による深掘り
活用フレームワーク:カスタマージャーニー
顧客インタビューや観察調査を通じて、行動と課題を明らかにする
評価観点:仮説と実際のニーズに乖離がないか
顧客が「強い解決意欲」を持つ課題か
防げる失敗:顧客ニーズの理解不足
STEP 5|事業性を検討する:収益性とスケーラビリティの初期評価
活用フレームワーク:簡易収支シミュレーション
収益モデルを早期に検証し、赤字構造を回避する
評価観点:小規模検証フェーズで採算の目処が立つか
目標の期間で投資回収が可能か
防げる失敗:収益モデルの不十分さ
1次情報の重要性|さらに成功率を上げるために
新規事業の企画において、もっとも大きな落とし穴のひとつが「机上の空論」に陥ることです。市場データやレポートだけで検討を進めてしまうと、実際の顧客行動や本当の課題感とは乖離してしまう危険があります。
成功する新規事業の多くは、企画段階から一次情報を積極的に取り入れることで、企画の各フェーズにおける事実性を高めています。
一次情報が重要な理由
顧客の「生の言葉」から本質的な課題を発見できる
→ アンケートやレポートでは見えない、購買理由や不満点を把握できる
検証スピードが上がる
→ 机上で悩むより、顧客に直接確認することで仮説修正が早まる
社内を動かす説得力になる
→ 顧客の声という一次情報は、経営層や関係部門を動かす根拠として有効
具体的な取り組み例
顧客アンケート/インタビューを通じた顧客ニーズの確認
既存顧客へのヒアリングとフィードバック収集
試作品を用いた小規模なPoC(概念実証)
一次情報をもとに仮説を検証し続けることで、判断の精度は格段に高まります。逆に、これを怠ると「なんとなく良さそう」で進めた企画が、後から大きな軌道修正を迫られる原因になります。
終わりに|少しでも成功率を高めるために
新規事業の成否は、企画段階で大きく方向づけられるといったことをお伝えしてまいりあした。だからこそ、成功率を少しでも高めるためには、まずは抑えるべきポイントを整理し、確実に一次情報を取ることが欠かせません。
また成功率を高めるためにも、顧客や市場の「生の声」に触れながら企画を磨き込むことで、判断の精度は格段に向上します。是非新規事業に取り組む際には、当コラムのポイントを抑えることや、1次情報を用いてプロジェクトを進行することで、机上の空論にはらならない成功確率の高い新規事業を進めて頂けると幸いです。