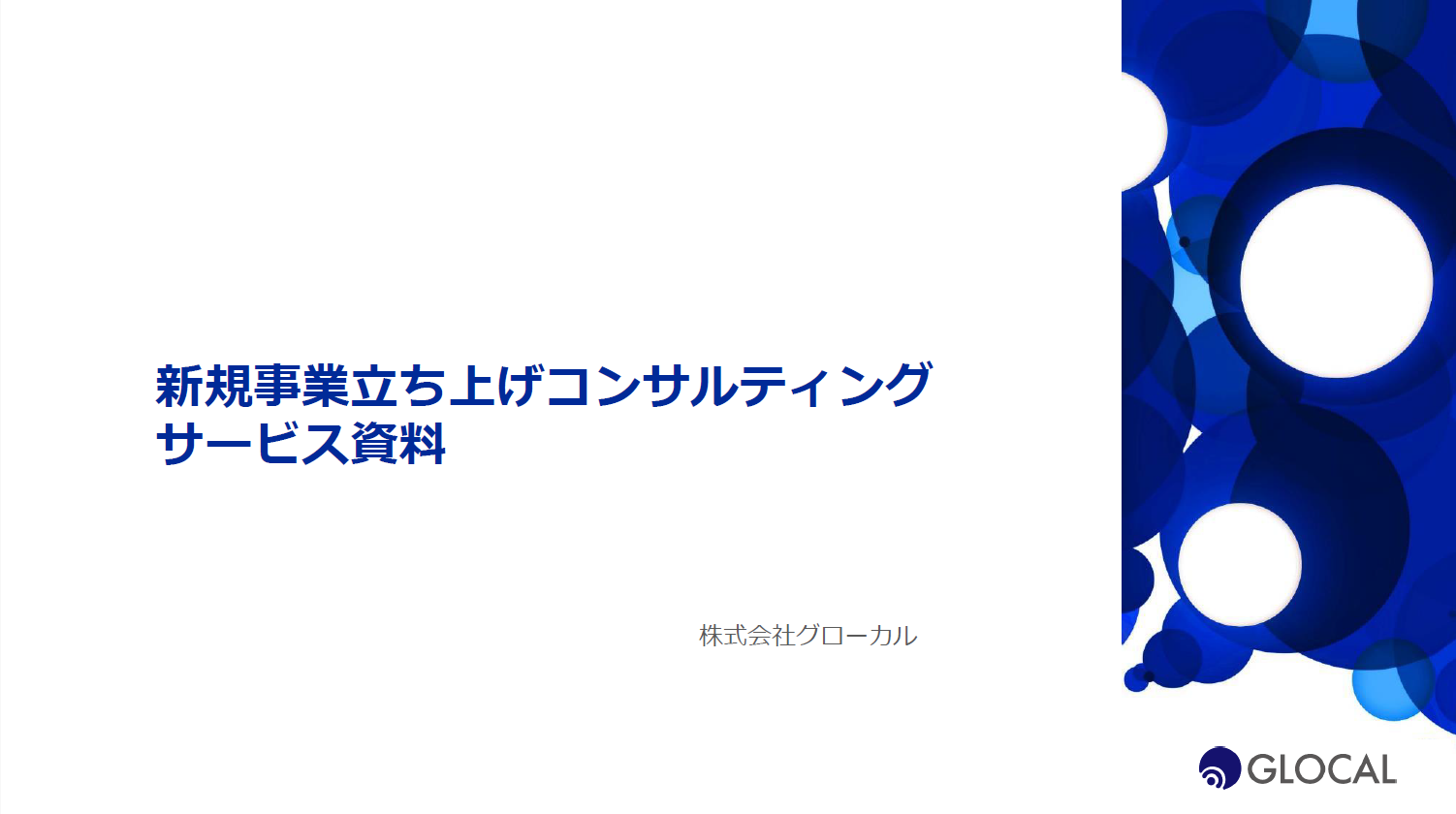新規事業の成功事例10選|成功企業に共通するポイントと失敗を防ぐコツを徹底解説

新規事業を立ち上げて成功させることは、多くの企業にとって大きな挑戦です。十分なリソースや計画を用意しても、思うように成果が出なかったり、途中で頓挫してしまったりという例も多いでしょう。
一方で、新規事業を軌道に乗せ、売上の第二の柱として育てている企業も存在します。こうした成功企業には、いくつかの共通する“法則があります。
「新規事業を始めたいが、まず何を意識すればよいか分からない」「 事業立ち上げの成功事例を参考に、自社の方針を考えたい」という方に向け、本記事では、実際の新規事業の成功事例を10選紹介するとともに、そこから見えてきた新規事業成功の共通点を解説します。
新規事業が成功するために必要な3つの視点
新規事業を成功させるためには、主に以下の3つの視点を押さえることが重要です。
①市場ニーズの把握
新規事業は、「誰かの困りごとをどう解決するか」に真剣に向き合うことから始まります。
企業側の都合や思いつきで始めたアイデアは、どんなに技術的に優れていても、ユーザーに受け入れられない可能性があります。
成功している企業の多くは、徹底した顧客理解に時間をかけています。ユーザーインタビュー、アンケート、データ分析、ペルソナ設計などを通じて、「本当のニーズ」や「表面化していない潜在ニーズ」を発見し、そこに対してニーズを満たす商品・サービスを提供しています。
つまり、「市場にどんな課題があり、誰が困っていて、何を求めているのか」を明確にすることが、事業成功の第一歩になります。
②自社の強みを活かす
市場のニーズを捉えたとしても、それを実現・提供できなければ意味がありません。そこで重要になるのが、自社の強みをどう活かすかという視点です。
例えば、既存の製造技術・流通ネットワーク・ブランド認知・人的リソースなど、すでに自社が持っている資産やノウハウを、新規事業に応用することで、立ち上げのスピードやコスト効率が大幅に改善されます。
成功事例では、既存の事業ドメインから応用可能な技術や知見を再活用して、他社がマネできない強みを差別化要素として取り入れているケースが多く見られます。
③スピード感のある仮説検証
新規事業の立ち上げにおいて、最も重要でありながら難易度が高いのが「スピード感をもった仮説検証」です。完璧な事業計画やプロダクトをつくり込んでから市場に出すのではなく、まずは小さく試して、顧客の反応を見ながら改善していくという姿勢が、現在の不確実な市場環境では求められています。
これは「リーンスタートアップ」と呼ばれる考え方にも通じています。
リーンスタートアップとは、最小限の機能を持つ試作品(MVP:Minimum Viable Product)をできるだけ早く市場に出し、実際の顧客からのフィードバックをもとに改良を重ねていくというアプローチです。
この方法をとることで、無駄な開発コストや時間を抑えながら、ユーザーが本当に求めているものに近づけていくことができます。「失敗しないように準備を重ねる」のではなく、「小さく失敗し、そこから素早く学ぶ」ことが、結果として成功を早める近道になるのです。
新規事業の必要性
多くの大企業が新規事業に取り組んでいるものの、思ったようにうまくいかないという声は少なくありません。リソースやブランド力がある一方で、意思決定の遅さや既存組織との摩擦により、新しい取り組みが前に進まないケースが多く見られます。
一方で、新規事業で成功した会社に共通しているのは、「新しいサービスのアイデア」そのものの優位性だけではなく、それを素早く形にし、顧客の反応をもとに柔軟に改善していく姿勢です。つまり、単なるひらめきではなく、仮説検証・組織体制・経営の後押しといった総合的な仕組みこそが、新規事業の成功要因となっています。
新規事業の成功率
新規事業の成功確率は、一般的にわずか1割以下とも言われています。新規事業が成功しにくい理由は、アイデアの不備だけでなく、市場ニーズの見誤りや、社内体制・スキームの不備など、多岐にわたります。多くの企業が「新規事業を成功させるには、何から始めれば良いのか分からない」と悩む中、重要なのは自社に合った新規事業スキーム(進め方の型)を設計することです。
たとえば、「仮説検証を前提としたリーンな進め方」「社内ベンチャー制度の活用」「オープンイノベーションによる共創」など、組織や業種に応じて最適なフレームが異なります。さらに、新規事業立ち上げでは、技術や資金以上に、「誰のどんな課題をどう解決するのか」という視点の明確化と、スピーディな意思決定・実行が求められます。
成功する企業は、この型を早期に整え、現場と経営が一体となってチャレンジを加速させています。限られたリソースの中でも、確率を高めるための仕組みづくりこそが、新規事業を「育つ事業」に変える第一歩となるのです。
中小企業の新規事業
中小企業にとって、新規事業は単なる新しい売上の柱をつくる手段ではありません。変化の激しい時代において、会社の未来を切り拓くための重要な挑戦でもあります。
ただし、新規事業を成功させるためには、スキルや資金だけでなく、「失敗を恐れず、まず動いてみる」という新規事業マインドが欠かせません。特に中小企業では、経営者や現場の一人ひとりがそのマインドを持ち、日常業務とは異なる視点で市場や顧客を見る姿勢が求められます。
また、すべての人がゼロイチの起業家になる必要はありませんが、「課題を見つけ、仮説を立て、小さく試す」という新規事業の素質は、後天的に身につけることが可能です。その素質を磨くことで、社員一人ひとりが事業を“自分ごと”として捉え、組織全体が挑戦体質へと変化していきます。
中小企業だからこそ持ち得るスピード感と柔軟性を活かせば、大企業にはない独自の価値を生み出すことができます。
新規事業の成功企業10選
実際に新規事業で成果を上げている企業の成功事例を、タイプ別にご紹介します。
成功事例タイプ1.大企業による事業転換・第二創業型
■富士フイルム|化粧品・医療分野に進出
カメラフィルムのトップメーカーとして知られていた富士フイルムは、デジタル化による写真フィルム需要の激減という危機に直面しました。
しかし同社は、写真フィルムの製造で培ったコラーゲンや抗酸化技術、ナノテクノロジーといった独自の技術資産に着目。
この強みを応用するかたちで、高機能スキンケア化粧品ブランド「アスタリフト」や、内視鏡・医療用診断機器などのヘルスケア分野に進出しました。
その結果、BtoB中心だったビジネスモデルをBtoCにも拡大し、現在では売上の中核を担う新たな事業の柱となっています。
参考:富士フイルム株式会社 ホワイト ジェリー アクアリスタ 開発の軌跡(https://ls-jp.fujifilm.com/astaliftbrand/contents/development-story-of-white-jelly-aquarysta/conversion-to-cosmetics/)
■日本経済新聞|電子版の有料会員化
紙の新聞が主力だった日本経済新聞社も、スマートフォンとSNSによるニュース消費の変化を背景に、既存モデルの見直しを迫られました。同社は、「紙を売る」から「情報に価値をつけて届ける」という本質に立ち返り、2009年に有料電子版を立ち上げます。
コンテンツそのものの質と深さを強みに、他メディアと一線を画した有料課金モデルを推進。現在では100万人以上の有料会員を抱える国内最大級のサブスク型メディアへと成長し、広告収益に依存しない安定した収益モデルを確立しています。
参考:「失敗する」と冷笑された日経電子版が成功した理由(https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/55080?utm_source=chatgpt.com#google_vignette)
■ソニー|PlayStationの大ヒット
AV機器や家電のイメージが強かったソニーは、1994年に家庭用ゲーム機「PlayStation」を発売し、エンタメ業界への本格参入を果たしました。当時のソニーにはゲーム機開発の実績はなかったものの、高い映像処理技術・音響技術・半導体開発力などを武器に、新しい体験価値を創出。
さらに、サードパーティのゲーム開発会社を支援し、ソフト面の充実を図るとともに、「IP(知的財産)戦略」によって独自のゲーム文化を築くことに成功しました。結果として、PlayStationシリーズは世界中で累計5億台を超える販売台数を記録し、ソニーにとっての「第二の柱」となる巨大事業へと成長しました。
参考:ソニー株式会社サービスメニュー全体像(https://sony-acceleration-platform.com/services)
成功事例タイプ2.スタートアップ的な立ち上げ・社内ベンチャー型
■京セラ × ライオン|仕上げみがき用歯ブラシの開発
「子どもの歯磨きをもっと楽しい時間にしたい」そんな親のリアルな悩みに向き合ったのが、京セラとライオンの共同開発プロジェクトです。
多くの親が経験する「子どもが歯磨きを嫌がる」という課題。この行動に着目したプロジェクトチームは、実際に親子の日常を観察し、歯磨きが“嫌なこと”ではなく“楽しい体験”になる方法を模索しました。
そこで生まれたのが、音楽が流れることで子どもが自然に口を開けたくなる仕組みを取り入れた「Possi」。京セラの骨伝導技術と、ライオンのオーラルケアに関する知見を掛け合わせ、短期間でプロトタイプを開発し、ユーザーテストを重ねながら半年ほどで商品化に成功しました。
参考:京セラ株式会社 子どもの仕上げ磨き専用歯ブラシ「Possi(ポッシ)」事業化および一般販売の開始について(https://www.kyocera.co.jp/news/2020/1208_annv.html)
■LIXIL|車椅子ユーザー向けの玄関ドアの開発
LIXILが開発した「DOAC」開発のきっかけは、たった2名の社員による「社内アイデア募集」への応募でした。彼らは車椅子ユーザーの自宅訪問を繰り返し、「家の中はバリアフリーなのに、玄関ドアの開閉が一人ではできない」という大きな課題を発見します。
課題の深さと市場のニッチさを確信したチームは、すぐに社内ベンチャー制度を活用し、ゼロから製品設計をスタート。開発とユーザーテストを並行して進め、約1年という異例のスピードで製品化にこぎつけました。
既存の住宅設備ビジネスとは異なるターゲット・課題に取り組むことで、LIXILはバリアフリー住宅という新たな市場開拓にも成功しました。
参考:ソニー オープンイノベーションによるDOAC誕生ストーリー(https://sony-acceleration-platform.com/article248.html)
成功事例タイプ3.DX・デジタル転換型
■リクルート|SUUMO・じゃらんnet
不動産情報誌「住宅情報」や旅行雑誌「じゃらん」は、かつては圧倒的な情報量と配布網を誇っていましたが、インターネットの普及により紙媒体の価値が急速に低下。そこで同社は早い段階から、「情報の提供」から「検索・比較・予約ができる体験」へとサービスを再設計しました。
ユーザー視点に立った高い検索性・UI/UXの最適化を徹底し、現在では「SUUMO」「じゃらんnet」ともに、Webサービスとして不動産・旅行分野のトップブランドに成長。メディア企業からデジタルプラットフォーマーへの進化を遂げた新規事業の成功事例です。
参考:NYマーケティング 不動産業界のSEO覇者「SUUMO」のSEOを徹底分析(https://ny-marketing.co.jp/blog/portal-ec/suumo/)
■サイバーエージェント|ABEMA
ニュース、ドラマ、音楽、アニメ、スポーツなど多様なジャンルを24時間無料で配信する「ABEMA」のスタイルは、従来のテレビ放送とは異なる価値を提供しており、若年層を中心に圧倒的な支持を獲得。
また、リアルタイム配信とアーカイブを両立させた設計や、コメント機能による双方向性の強化など、「視聴体験」を再発明したUI/UX設計も大きな特徴です。ABEMAは、広告収益だけでなく、PPV(有料配信)やプレミアム会員による収益モデルも構築し、テレビ業界に一石を投じる存在として確固たる地位を築いています。
参考:サイバーエージェント ABEMAにおけるサービスブランディング(https://developers.cyberagent.co.jp/blog/archives/36057/)
■PayPay|QRコード決済で急成長
ソフトバンクとヤフーがタッグを組み、2018年にリリースされたモバイル決済サービス「PayPay」は、キャッシュレス化の波を捉えてわずか数年で国内トップシェアを獲得する急成長を遂げました。
その原動力は、なんといっても大胆なプロモーション戦略。「100億円あげちゃうキャンペーン」などの大型施策を次々に展開し、わずか1年で1,000万人以上の利用者を獲得。
既存の金融機関にはできなかったスピードとマーケティングの切り口で、短期間で新しい決済習慣を作った好例です。
参考:PayPay 事例紹介(https://paypay.ne.jp/store-case/)
成功事例タイプ4.既存業態のブランドリニューアル型
■ワークマン|ワークマンプラス
もともとは作業服や安全靴を扱う専門店として、主に建設・運送業のプロユーザーを顧客としていたワークマン。しかし近年、「機能性が高くてコスパが良い」という特長が一般消費者の間でも注目され始めたことを受け、同社はアウトドア・スポーツ向けの新ブランド「ワークマンプラス」を立ち上げました。
店舗デザインを一新し、SNSやYouTubeなどを活用した発信を強化することで、女性・主婦層・ファミリー層などこれまでとは異なるターゲット層を獲得。プロ向けの品質を、一般向けに再編集するという発想が成功を呼んだ新規事業の成功事例です。
参考:TCG REVIEW ワークマンのブランディング戦略 「ワークマンプラス」(https://review.tanabeconsulting.co.jp/modelcompanies/24682/)
■三菱商事|スープストックトーキョー
大手商社の三菱商事が飲食業に参入したプロジェクトとして生まれたのが、食べるスープ専門店「スープストックトーキョー」です。
忙しい女性がひとりでも、気持ちよく食事ができる場所をコンセプトに、カフェのような空間、選び抜かれたスープ、そして温かみのあるブランドストーリーを設計。価格帯も比較的高めに設定しながらも、コンセプトに共感したファンの支持を集め、現在では百貨店・駅ナカなど都市型店舗を中心に、安定した成長を続けています。
参考:定期購入EC通販 Soup Stock Tokyoの「秋野つゆ」の成功事例からみるペルソナ設定について(https://whattoeatbook.com/persona-3/)
成功事例に共通する5つのポイント
① 目標と課題が明確である
新規事業が迷走してしまう大きな原因の一つが、「誰のどんな課題を解決するのか」が曖昧なまま走り出してしまうことです。一方で成功している事業は、開始段階から明確なターゲット設定と顧客課題の特定がなされており、全ての意思決定がその軸に沿って動いています。
たとえば「子育て世代の◯◯に不満がある」といった具体的なシーンや感情に焦点を当て、そのペルソナに対する“価値の提案”が一貫していることが特徴です。誰のために、なぜやるのか。その原点を最初に明確にしたことで、ブレない事業づくりが可能になっています。
②自社の強みをうまく活用している
全く新しいことにチャレンジする一方で、自社がこれまで培ってきたリソースやノウハウをうまく活かしている点も、成功事例に共通するポイントです。
たとえば、メーカーであれば「研究開発力」や「製造技術」、メディア企業であれば「情報発信力」や「ブランド認知度」など、既存の資産を土台にすることで、他社が簡単に真似できない競争優位性を築いているのです。
また、現場の知見や社内の人的ネットワークなど、目に見えにくい“組織資産”も活用されており、「完全なゼロからの起業」ではなく、「強みの再編集」としての事業立ち上げが多く見られます。
③小さく始めて改善を重ねている
成功事例の多くが共通して採用しているのが、MVP(Minimum Viable Product:最小限の機能で構成された製品)を使ったスモールスタートです。
最初から完璧な商品やサービスを作ろうとするのではなく、まずは最小限の価値を提供できる形で市場に出し、実際のユーザーからのフィードバックをもとに改善を繰り返すというプロセスが取られています。
このアプローチにより、無駄な開発コストや時間を削減しながら、本当に求められる価値を見つけ出すことができます。
④ 社内外との連携がスムーズである
成功する新規事業は、組織の垣根を越えた連携体制が整っているという点も見逃せません。
部署間の連携だけでなく、社外パートナーやスタートアップ、自治体・大学などとの協業を柔軟に活用し、スピードと多様性を両立した推進体制を構築しています。
特に最近では、オープンイノベーションや共創の機会を積極的に取り入れ、自社内ですべて完結させないという柔軟な発想が、事業化を加速させています。
また、社内での巻き込み力も重要な要素。現場やバックオフィス、経営層との連携がスムーズなほど、意思決定のスピードと実行力が高まります。
⑤経営層の強いコミットメントがある
新規事業は不確実性が高く、短期的な利益が見えにくいため、現場だけでは推進しきれない場面が多くあります。その中で、成功事例に共通しているのが経営層からの明確な後押しとリーダーシップです。
「この事業は会社として取り組むべきだ」というトップのメッセージがあれば、組織全体が一体となってサポートし、社内の調整やリソース配分もスムーズに進みます。また、予算や人材の確保、最終意思決定の迅速さなど、トップダウンでのサポートがあるからこそ、初動が速く、事業化までのスピードも早まるのです。
失敗を防ぐために意識すべき落とし穴
①社内調整に時間をかけすぎ、リリースが遅れる
新規事業はスピード勝負にも関わらず、各部署や関係者との調整に時間がかかりすぎると、市場のチャンスを逃してしまうことがあります。最低限の合意でまずは動き出し、走りながら調整する柔軟さが求められます。
②顧客の声を無視し、独りよがりなサービスに
社内の思い込みだけで商品やサービスを作ってしまうと、市場のニーズとズレたプロダクトになりがちです。顧客インタビューやユーザーテストなどを通じて、リアルな声を反映する姿勢が不可欠です。
③検証せずにいきなり大規模投資してしまう
仮説が正しいかを確かめる前に、大きな金額や人員を投入してしまうと、失敗のリスクが拡大します。まずは小さく試して、確実性が見えた段階でスケールするのが安全です。
④担当者任せになり、経営層の温度感が低い
現場任せの状態では、社内調整や意思決定が進まず、プロジェクトが停滞する原因になります。経営層が方向性を示し、「会社としてやる事業だ」と明確に打ち出すことが重要です。
⑤組織としての支援体制が整っていない
人・予算・評価制度など、仕組みが整っていないと、担当者が孤立しやすく、継続的に進められません。新規事業専用のサポート体制や意思決定ルートを整備することが、実行力を高める鍵になります。
よくある質問(FAQ)
Q1:新規事業のアイデアはどう見つければいいですか?
→ 社内の顧客対応部門や現場の声、トレンドリサーチなどが有効です。日常の不便や顧客の困りごとに目を向けましょう。
Q2:立ち上げにはどのくらいの期間が必要ですか?
→ MVP(最小限の価値を持つ製品)であれば、1〜3ヶ月でリリースできることもあります。
Q3:中小企業でも新規事業は可能ですか?
→ むしろ機動力や現場の近さを活かせる中小企業こそ向いています。スモールスタートが基本です。
まとめ
新規事業の立ち上げには、常に不確実性とリスクがつきまといます。しかし今回ご紹介した10の成功事例からわかるように、企業の規模や業種を問わず、本質を押さえた戦略と行動力があれば、新たな価値を創出することは十分可能です。
新規事業において重要なのは、「完璧を目指すこと」ではなく、「小さく始めて、すばやく学び、着実に前進すること」です。まずは目の前の小さなアイデアを、行動に移すところからスタートしてみましょう。